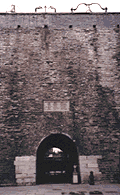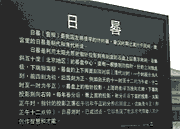| 5) 中国の影響の具体例 |
|
| 目に見えるものとしてみれば土木・天文。例えば佐賀にある石井樋という河川施設。葉隠にも出てくる成富兵庫茂安が造ったという治水の仕組み。あれも中国にそっくりそのままがあるそうです。あるいは天文関係でいうと、台形の山を築いて上に天文台を造るんですが、それが各藩にあって、例えば会津若松に行きますと、藩校日新館にある。江戸にもいくつもあった。それとそっくりの規模の大きなのが今も北京の観象台として残っています。これは元の時代からのものです。 |
|
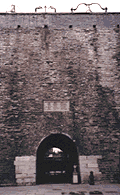 |
*中国・北京に残る元の時代からの天文台(観象台)
内部は部屋になっており、屋上には各種の測定用機器が置いてあります。 |
|
|
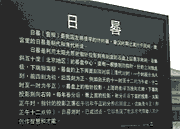 |
*日時計の説明板
日時を知り、暦を公布することは、中国で、そして日本でも支配者であることの象徴でした。これは北京の故宮太和殿前におかれた日時計の説明板です。
|
|
|
|
|
| 実は経度が中国と異なる日本では、「あくまでも中国を参考にしながらも」日本独自の暦を作る必要があり、以下に述べるとおりの一種の国粋主義の発現として、こうした天文台が作られました。この「あくまでも中国を参考にしながらも」つまり中国を基準としながら、というのが、これからの話しのミソです。 |
|
 |
*「授時暦」の解説書
江戸時代に出版された中国の暦である「授時暦」の解説書。「授時暦」は遠くイスラム暦を元にしています。
2の3)に紹介する水戸黄門、保科正之と親しかった渋川春海は、彼らの国粋主義を日本独自の暦「貞享暦」として実現させた人物である、といえます。
|
|
|
そして目にみえないものとして大切なものが、儒教、あるいはその根本にある大義名分論だと思います。
金、元、清などの異民族に長い間圧迫されてきた中国では、この数百年の間に一種の国粋主義ともいえる大義名分論が醸成され、南北朝時代や徳川初期の日本にも極めて大きな影響を与えました。
|