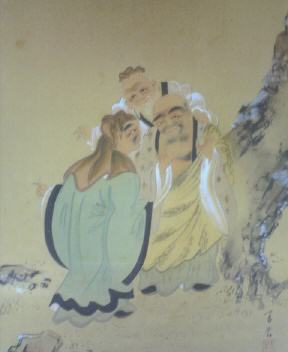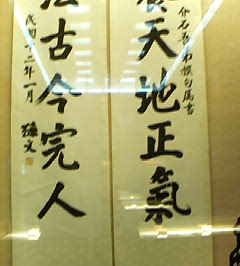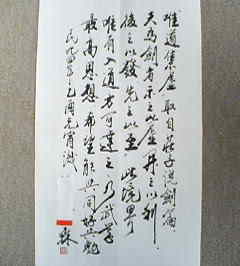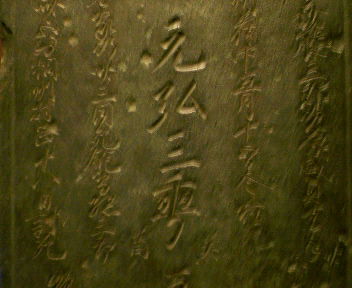|

|
1年前の「事務室だより」です。
この写真は、先日、葵祭が行われた京都の下賀茂神社。塀のようなものは社殿の入り
口、正面に建っているものですが、沖縄では「ピンプン」と呼ばれるものと同じでしょ
う。右回り、左回りの話があります。
このピンプン、実は中国では塀風。
また、私の知るところでは、礼記に「大夫士、君門を出入するには、闑(げつ)
の右よ
りし、閾(よく)を踏まず」とあり、「敷居を踏むな」などという話もここに出ている
ようですが、大いに関わりを感じます。
桓武天皇は、その母や後援者の関係で、渡来人の多い京都に都を移され、この神社を尊
崇されました。
その日本の基底ともいうべきここに、こんな国際的なものが(実は沢山・・というよ
り、本質的に)あることに気宇壮大なものを感じ、世界と和することを考えたいと思い
ます。
★5月31日
世界のどこにもおかしな政治家はいるものですが、法治主義をわきまえない政治家は
困りものです。
少し前、シュワ現知事のサインの入った公文書を私蔵していた我が国の法務大臣。最
近では、今回国民党の連戦候補と組んだ台湾の宋元総統候補が選挙法を無視して票の数
え直しを迫り、みんなからあきれられました。
しかるに今晩の新聞を見て、フセイン大統領逮捕時の拳銃をブッシュ大統領がホワイ
トハウスに置いてみんなに見せているとはアメリカの法治主義も?では困ったもので
す。それには様々な情報も含まれているはず。兵士の命がそれで救われるとするなら大
変です。格好だけ軍服を着てみせてもしかたありません。そんな「軽さ」に対して日本
は・・
そういえば、2・26事件の匂坂検事の保管していた調書につき、青年将校であった
池田俊彦さんから批判があったこともありました。
★5月30日
ラストサムライのDVDが出始めて、再びミニ武士道ブームかと思われます。
しかしそれにしても、相変わらずの新渡戸さんの「持ち上げ」にはあきれてしまいま
す。新聞に出ていた「負けるが勝ち」が新渡戸武士道だなんて、大学の先生ともあろう
ものが一体あの本をまともに読んでいるのでしょうか。新渡戸さんが教育者ということ
と、できた本とは別なんです。
国家は個人に先立ち、と言って親が子を差し出すだとか、優秀な兵器より精神だと
か、もっと法的にいえば封建君主は国民には責任を負わず天にだとか、じっと目をこら
して読めば読むほどおかしな本だし、日本的ではない奇怪な本。
「太平洋の架け橋」なんかじゃありません。これを「読み切る力」が日本人にはそれ
こそ必要です。それにはアジア全体の知識もあったに越したことはありませんが。
★5月27日
昔、古い言葉になりますが「戦時中」、戦意高揚をぶち上げて若者を戦地に送ってい
た人が、戦後はくるりと向きを変えて共産主義礼賛のようなことを言っているのには気
を付けよと再三言われたことがあります。
最近はその反対で、昔(といっても2,30年前)共産主義礼賛のようなことを言って
いた人間が、全く逆の行動をしているのを見ます。掲示板に書きました。
一体、人間の一貫性、筋の通し方とは何か、考えてしまいます。
最近の裁判を見て考えたことです。少なくとも、昔左翼の今右翼なんていう人物は信
用できません。
★5月21日
先日の韓国の新聞・朝鮮日報の社説、「小泉首相の訪朝は、私たちに『なぜ国が存在
するか』という問いを投げかけている。自国民の保護という最も基本的な義務を怠る国
は『国らしい国』と言えないという教訓を日本から学ばなければならないのが悲しいば
かりだ。」と。
こんなに我が国を持ち上げて下さるなんて、正に面映い感じですが、むしろこういう
視点を持って国家を考えている隣国のメディアに、敬意を表したいと思います。
再三述べるとおり、国民に責任を負わず、天に負っているのが立派な封建君主などと
言っている本(新渡戸稲造「武士道」)がたくさん売れている我が国の現状と、この社
説の視点は対極です。
★5月17日
韓国憲法裁判所での大統領弾劾裁判の判決にあたり、各裁判官が言い渡しに際して、
マスコミのインタビューに応じる人、応じない人、様々な人がいたこと、その答えの内
容、そうしたことが報ぜられていることに、進んでるなーと感じました。
日本のように、何やら良くわからない人の裁判ではないのです。
大陸は世界共通だな、と時に感じてしまいます。
★5月16日
昨日の朝刊一面にあった首相の年金「未加入」と北朝鮮訪問を武士道で斬るどうなる
でしょうか。
この博物館では「一味同心」の武士道こそ本物、というわけですから、未加入の人は
そもそも一味も同心もしていないわけ。つまりは共存同栄相互扶助的な保険の仕組に同
心しておらず、それでいて、税金同様に取りたてる保険の仕組を提案しているというわ
けですから、自己矛盾の極地。
つまりこのことは「国家像」あるいは国造りの根本の話です。
そして、そのような人が北朝鮮へ救いに行こうというのですから、いつもいうとお
り、日本は病気の体で戦争するようなもの、ということになってしまいます。
このあたり、国家の組織と作用をきちんとさせなければと思いますが…。
★5月13日
今(電車の中で)読んでいるのが「近世私法史」(F・ヴィーアッカー。鈴木禄弥
訳)。本文だけでも七百数十頁の大著で、ドイツの私法を、周辺の様々な思想が流れ込
む道筋を追って記した素晴らしい本。こういう本は日本にはないかなーと思わざるをえ
ません。
しかし、素晴らしさは、それを訳した鈴木先生についても言えるわけで、先生はこの
大著を訳されただけでなく、その原本の正誤表を末尾に付け、その量がまたすごい。原
著者にも確認されたとのこと。
変な話ですが、これだけ間違いがあっても「名著」ということは、これまた文化、あ
るいは「本観」の違いかなと思います。
誤植恐るることなかれ、中身で勝負、とも。正に葉隠武士道でいえば「実」です。と
ても比べものにはなりませんが、上の自著も実は誤植があちこちになのですが、独創性
だけはあるはず。ただし、学問的裏づけはもっと必要。
★5月3日
憲法記念日。この博物館では、武士道を、国民に義務を賦課する人物の倫理あるいは
理念と考えていますから、必然的に憲法を念頭に置くことになります。
そして、江戸時代中期以降の庶民は、新渡戸さんのいう「天や祖先」に責任を負った
武士からいわばご無理ごもっとも式に義務を賦課されるだけだったのですが(五人組とか
一揆の話は別。行政法の大きな枠組として)、それでは自身が責任を負わなくていい代
わりに、いわば子羊みたいな「撫民」つまり撫でられるだけの存在になってしまいま
す。しかし、そんなことで済むような現代ではありませんよね(年金の問題を見て
も)。
ですから、むしろ国民自身が責任を持った、中世武士のような兵農未分離の一騎当千
の兵になるべし、と言っているわけです(国民は自由と責任を)。
ところが先日、一度お会いしたこともあるある有名な先生、あるメディアで「今どき
個の自覚なんて言っているのは古いのであって、長年にわたって築きあげた武士道精神
が大事」、とか言われていました。その武士道精神とかいわれるのは、例の近世武士道
のようですが、「個の自覚」なるものを勝手な利己主義と一緒にされているようで、中
世武士道が葉隠や吾妻鑑の放生に見られるような「他の個」をも大切にする公共的な考
えであることをご理解いただいていないようです。
戦時中、個人主義と利己主義とを混同する議論がありましたが、夏目漱石の「私の個
人主義」でも読んでみたら、と言いたくなりました。
|